
|
意賀美神社、雨降りの滝 |

|
古い伝説があります。元慶八年(西暦884年)泉州地方を襲った干ばつに対し、時の天皇であった陽成天皇の命により、大学者として知られた菅原道真に祈雨させたところ、「泉州意賀美というところの滝壺をさらえば雨が降るであろう。」という神のお告げがあったので、早速滝壺をさらえたところ、雨が降って田畑を潤したと云われています。後に、菅原道真のこの功績を称えて、この地に意賀美神社が建立されたと云われています。(阿形賢一著、岸和田市史より) しかし境内の礎石に天平4年の銘があり奈良時代にはすでに存在した? 場所は、土生瀧町にありますが平安時代には加守郷一帯の住民の信仰があったそうです。(土生神社由緒より)その後土生神社、沼天神が出来て、現在の両瀧町の村社となっていますが、江戸時代には岡部公自ら降雨の祈願に訪れるなど、八田の矢代寸神社(岸和田藩一の宮)とともに岸和田藩にとって重要な信仰の対象であったようです。明治時代には村々の神社は郷社(土生瀧は加守郷であり沼天神)に合祀されましたが、意賀美神社はそのまま残りました。(ただし宮司さんは沼天神のかたです。) 地車はその土生瀧町、阿間河瀧町が宮入します。葛城町もここの宮さんに参りますが、進入路の前でお払いをうけるだけです。 修斉小学校の校歌で「意賀美の宮の昇り竜」というフレーズがあるように地区の象徴的な宮さんです。 |

|

|
| 宮さん内より進入路をのぞむ。 |
すごい坂です。 昔は未舗装でした。 |

子供の時はよくここで泳ぎました。(ただし危険なので、今は遊泳禁止?)
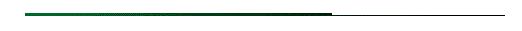

|
kuzuwaka@hotmail.com |