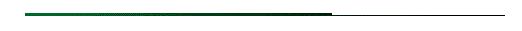|
修斉地区について |
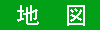
|
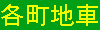
|
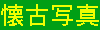
|
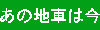
|
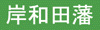
|
また、歴史は古く物部氏の時代(飛鳥時代)あたりから八田の宮さん(矢代寸神社=やしろぎじんじゃ)があったと小学校で習いました。江戸時代には岸和田藩領に属し、津田川など岸和田城の堀の水を導いていただろう川の上流でありますので貝塚市麻生郷地区や、隣の旭・太田地区とともに岸和田藩と深い関係があったと推測されます。 実際、だんじりについても土生滝町や阿間河滝町のように岸和田藩史に登場したり、神須屋町の「オッシャンシャン」ように旧市地区と同じ伝統が残っている(私自身は未確認)町もあります。 明治維新以降は、有真香村(郵便局に名前が残っています)と称し、昭和15年に土生郷村(今の旭・太田地区)に続いて岸和田市に合併し現在にいたっています。 観光スポットとしては岸和田市の中央に位置しどこからでも見える象徴的な山である神於山への登山口(土生滝町、北阪町)、土生滝町にある意賀美神社(おがみじんじゃ)にある雨降りの滝、 真上町の捕鳥部萬の墓(実際は天神山2丁目)、 神須屋町の泉州玉葱発祥の碑(実際は土生新田町)、行遇堂、岸和田藩主岡部家の菩提寺である泉光寺(実際は土生町)、明治天皇駐蹕(ちゅうひつ)記念碑(実際は土生町)、北阪町の観光みかん園など 周辺地域の無形文化財としては、鼓おどり(土生町)、葛城おどり(塔原町)がある。 修斉地区各町について(あいうえお順) 阿間河瀧町(あまがたきちょう) 私が小学生の時に聞いた話では、修斉地区の古い名称である「あまか(ありまか)」の滝(もちろん雨降りの滝)の村というのが名前の由来らしい。土生滝町から津田川の橋を渡ると町内です。古くからの狭い道と坂道でだんじりの曳行はたいへんです。町内から意賀美神社への参道が延びており岸城塔原線が昭和になって開通するまでは阿間河瀧だんじりの宮入はここを通っていたと推測されます。後述の土生滝とは江戸時代にはあまり仲がよくなかったそうで、だんじりの宮入のことなどのもめ事で、しばしば岸和田藩が仲裁に入ったらしい。もちろん現在は仲がいいようです。 葛城町(かつらぎちょう) 説明 北阪町(きたさかちょう) かつて南上町、真上新田などの飛び地でありましたが、昭和18年に北阪町となりました。神於山の中腹に北阪八幡宮があります。みかん山の町、観光みかん園が有名。むかしはここの子供たちは土生滝町のだんじりを曳いていました。 神須屋町(こうずやちょう) 修斉地区で最もやり回しが見られる交差点である神須屋交差点がある町。矢代寸神社宮入後、御輿を先頭に5台のだんじりがこの町にあるお旅所までパレードします。 八田町(はったちょう) 旭・太田、修斉地区の5台のだんじりが宮入する矢代寸神社のある町。葛城町は昔、八田団地と称されていたことがあります。 土生滝町(はぶたきちょう) 私が小学生のとき聞いた話では、名前の由来は土生郷(旭・太田地区の土生町)から雨降りの滝周辺に移り住んだ人々の村から、土生の滝村という意味とのことです。意賀見神社へは土生滝側からも古い参道、鳥居がありますので岸城塔原線開通前はここから宮入していたと推測されます。現在は阿間河滝町とともに岸城塔原線から急な坂を下って意賀美神社の東側から境内まで入ります。修斉小学校のある町です。 真上町(まかみちょう) 戸数70程の小さな町ですが古くからだんじりを所有しています。以前、葛城町子供会はこのだんじりを曳かせてもらっていました。修斉地区のほぼ中心に位置していますので祭礼の時には何度かこの町にだんじりが集合し年番さんの御挨拶があります。天神山3丁目あたりに氏神さまである真上神社があります。 |
||